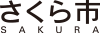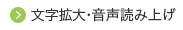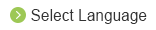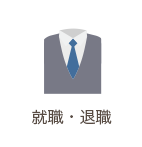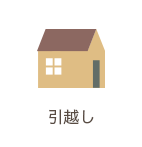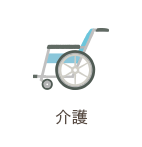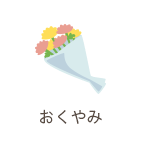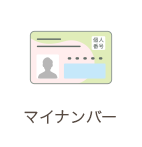子どもの予防接種
感染症の発生およびまん延を防ぐため、各種予防接種を実施しています。こどもを感染症から守るために、適切な時期・接種回数等に注意しながら、計画的に予防接種を受けましょう。
長期療養を必要とする疾病にかかった方の定期予防接種について
長期にわたる療養を必要とする疾病(厚生労働省令で定められた疾患)にかかったために、定期の予防接種対象年齢内に予防接種を受けられなかった方も、一定期間内であれば、定期の予防接種として接種できます。対象者に該当する方はご連絡ください。すでに自己負担にて接種された予防接種については対象となりませんのでご了承ください。
麻しん風しん混合ワクチンの定期予防接種の期間延長について
令和6年度の麻しん及び風しんの定期の予防接種に用いられるMRワクチンの供給状況に鑑み、第1期、第2期の対象者であってMRワクチンの偏在等を理由に期間内に接種できなかった方について、予防接種法施行令第3条第2項及び予防接種法施行規則第2条の8第4項に基づき、接種期間を2年間延長することになりました。
対象
下記の生年月日に該当する方で、MRワクチンの不足等により令和6年度の定期接種期間内にワクチンの接種が受けられなかった方
- 第1期:令和4(2022)年4月2日から令和5(2023)年4月1日生まれの方
- 第2期:平成30(2018)年4月2日から平成31(2019)年4月1日生まれの方
期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
予防接種の種類
定期予防接種
指定医療機関(県内相互乗り入れ事業協力医療機関(新しいウィンドウが開きます))で接種する場合は自己負担額なしで接種可能です。
指定医療機関以外で接種する場合は医療機関宛の「予防接種依頼書」が必要になりますので、事前に健康増進課にて手続きをお願いします。
| 種類 | 接種方法 | 接種期限 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ロタ (生ワクチン) |
1価 |
生後6週~24週までに27日以上の間隔をあけて2回接種 安全性の観点から1回目の接種は生後14週6日までに実施することを推奨 |
生後24週0日まで | ||||
| 5価 |
生後6週~32週までに27日以上の間隔をあけて3回接種 安全性の観点から1回目の接種は生後14週6日までに実施することを推奨 |
生後32週0日まで | |||||
|
5種混合 (不活化ワクチン) |
※令和6年度より定期接種開始(4種混合+ヒブ) 初回:20日~56日までの間隔で3回接種(標準は生後2か月~7か月未満) |
7歳6か月の誕生日の前日まで | |||||
|
ヒブ (不活化ワクチン) |
※5種混合接種の方は対象外 | 5歳の誕生日の前日まで | |||||
| 標準的な接種期間 | 生後2か月~7か月未満で接種開始 |
初回:27日~56日までの間隔で3回接種 追加:3回目接種後7か月~13か月の間に1回接種 2回目と3回目は1歳未満までに終了させ、1歳を超えた場合には行わない(追加接種は可能) |
|||||
| 標準以外 |
生後7か月~1歳未満で接種開始 |
初回:27日~56日までの間隔で2回接種 追加:2回目接種後7か月~13か月の間に1回接種 2回目は1歳未満までに終了させ、1歳を超えた場合には行わない |
|||||
| 1歳~5歳未満で接種開始 | 1回接種 | ||||||
|
4種混合 (不活化ワクチン) |
第1期 |
※5種混合接種の方は対象外 初回:20日~56日までの間隔で3回接種(標準は生後2か月~12か月) 追加:初回終了後、おおむね1年後に1回接種(標準は初回終了後12か月~18か月) |
7歳6か月の誕生日の前日まで | ||||
|
小児用肺炎球菌 (不活化ワクチン) |
標準的な接種期間 | 生後2か月~7か月未満で接種を開始した場合 |
初回:27日以上の間隔で3回接種 2回目と3回目は2歳未満(標準は1歳未満)までに終了させ、2歳を超えた場合は行わない。また、2回目が1歳を超えた場合3回目は行わない。(追加接種は可能) |
5歳の誕生日の前日まで | |||
| 標準以外 | 生後7か月~1歳未満で接種を開始した場合 |
初回:27日以上の間隔で2回接種 2回目は2歳未満(標準は1歳未満)までに終了させる。2回目が2歳を超えた場合は行わない。(追加接種は可能) |
|||||
| 1歳~2歳未満で接種を開始した場合 | 60日以上の間隔で2回接種 | ||||||
| 2歳~5歳未満で接種を開始した場合 | 1回接種 | ||||||
| B型肝炎 (不活化ワクチン) |
生後2か月~9か月未満で接種を開始 | 3回接種 初回:27日以上の間隔をおいて2回接種 追加:1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回接種 |
1歳の誕生日の前日まで | ||||
| 結核(BCG) (生ワクチン) |
生後5か月~8か月までに1回接種 | 1歳の誕生日の前日まで | |||||
|
2種混合 (不活化ワクチン) |
【第2期】 | 11歳以上13歳未満で1回接種(標準は11歳~12歳) | 13歳の誕生日の前日まで | ||||
|
麻しん風しん混合 (生ワクチン) |
【第1期】 |
生後12か月~24か月の間に1回接種 |
2歳の誕生日の前日まで | ||||
| 【第2期】 | 小学校入学前年度(年長児)の間(4月1日~3月31日)に1回接種 | 3月31日まで | |||||
| 特例措置 |
下記の生年月日に該当する方で、MRワクチンの不足等により令和6年度の定期接種期間内にワクチンの接種が受けられなかった方
|
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | |||||
| 水痘(生ワクチン) | 1回目:生後12か月~15か月までに1回接種 2回目:1回目接種終了後、6か月~12か月までの間隔をおいて1回接種 |
3歳の誕生日の前日まで | |||||
| 日本脳炎 (不活化ワクチン) |
【第1期】 | 初回:6日~28日間隔で2回接種(標準は3歳) 追加:初回接種終了後、おおむね1年後に1回接種 |
7歳6か月の誕生日の前日まで | ||||
| 【第2期】 | 9歳~13歳未満の方で1回接種 | 13歳の誕生日の前日まで | |||||
|
特例措置 |
ただし、平成17年4月2日~平成19年4月1日生まれの方で、休止により接種できなかった不足分は、助成対象になります。(20歳の誕生日の前日まで) | ||||||
|
子宮頸がん (不活化ワクチン) |
2価 | 小学校6年生から高校1年生に相当する年齢の女性(標準は中学1年生) |
1回目から1か月の間隔をおいて2回目、1回目から6か月の間隔をおいて3回目。 |
高校1年生に相当する年度の3月31日まで | |||
| 4価・9価 |
1回目から2か月の間隔をあけて2回目、1回目から6か月の間隔をあけて3回目。 ※9価については、1回目を15歳になるまでに接種開始した場合は、6か月の間隔をおいて2回目を行う。2回接種で完了することが可能。 |
||||||
| 経過措置 |
次の(1)(2)の方は、全3回の接種を公費で完了できるよう、キャッチアップ接種の経過措置が設けられています。 (1)キャッチアップ接種対象者(平成9年度~平成19年度生まれの女子)のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方 (2)令和7年度に、新たに定期接種の対象から外れる方(平成20年度生まれの女子)で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方 |
令和8年3月31日まで | |||||
任意予防接種
おたふくかぜ予防接種
接種方法
- 1回目:生後12か月~24か月までに1回接種
- 2回目:小学校入学前年度(年長児)の間(4月1日~3月31日)1回接種
助成金額
1回目、2回目とも3,000円
その他
- 接種金額から助成金額を引いた金額は自己負担になります。
- 塩谷郡市内の指定医療機関には予診票がおいてありますのでご利用ください。
- 指定医療機関以外(塩谷郡市外の医療機関等)で接種する場合は、医療機関宛の「予防接種依頼書」が必要になりますので、事前に健康増進課にて手続きをお願いします。
![]() おたふくかぜの予防接種を希望する方へ(pdf 220 KB)
おたふくかぜの予防接種を希望する方へ(pdf 220 KB)
おたふくかぜ予防接種における助成期間延長の特例措置について
現在、一部メーカーのおたふくかぜワクチンが出荷停止になっていることから、ワクチン不足が生じております。
ついては、下記対象者に対し、おたふくかぜ予防接種の助成期間を延長することとしました。
何かご不明な点等がありましたらご連絡ください。
対象
下記の生年月日に該当する方で、おたふくかぜワクチンの不足等により助成期間中に接種を受けられなかった方
- 1回目:令和5(2023)年4月2日から令和6(2024)年4月1日生まれの方
- 2回目:平成31(2019)年4月2日から令和2(2020)年4月1日生まれの方
延長期間
令和9年3月31日まで
その他
- 接種する際には医療機関に直接予約してください。
- 指定医療機関以外(塩谷郡市外の医療機関等)で接種する場合は、医療機関宛の「予防接種依頼書」が必要になりますので、事前に健康増進課にて手続きをお願いします。
インフルエンザ予防接種
令和7年度のインフルエンザ予防接種については、令和7年度インフルエンザ予防接種の助成(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
指定医療機関以外で接種する場合について
指定医療機関以外で予防接種をする場合は、医療機関宛の「予防接種依頼書」が必要になります。事前に健康増進課にて手続きをお願いします。
定期予防接種を指定医療機関以外で接種するとき
病気・出産などによる里帰りなどの理由で、県外で定期予防接種を受けるとき、また、県内でも「栃木県内定期予防接種相互乗り入れ事業」の協力医療機関以外で予防接種を受ける場合には、医療機関宛の「予防接種依頼書」が必要です。接種前に健康増進課にて手続きをお願いします。
栃木県内定期予防接種相互乗り入れ事業の協力医療機関(栃木県医師会ホームページ)
インターネットでの申請
こちらから申請してください。申請内容に基づき必要書類を郵送します。
窓口での申請
健康増進課窓口で、![]() さくら市指定外医療機関定期予防接種申込書(pdf 75 KB)を記入してもらいますので、健康増進課へお越しください。
さくら市指定外医療機関定期予防接種申込書(pdf 75 KB)を記入してもらいますので、健康増進課へお越しください。
予防接種後は、予診票と領収書、通帳のコピーを添付して、![]() 予防接種費助成申請書兼請求書(pdf 153 KB)を提出してください。
予防接種費助成申請書兼請求書(pdf 153 KB)を提出してください。
※医療機関の証明が必要です。1つの予防接種につき1枚の申請書に記入してもらってください。
※助成申請は、予防接種を受けた日から1年以内にお願いします。
任意予防接種を指定医療機関以外で接種するとき
インターネットでの申請
こちら(新しいウィンドウが開きます)から申請してください。申請内容に基づき必要書類を郵送します。
窓口での申請
健康増進課窓口で、![]() 指定外医療機関法定外予防接種申込書(pdf 57 KB)を記入してもらいますので、健康増進課へお越しください。
指定外医療機関法定外予防接種申込書(pdf 57 KB)を記入してもらいますので、健康増進課へお越しください。
予防接種後は、予診票と通帳のコピーを添付して、![]() 法定外予防接種助成申請書兼請求書(pdf 154 KB)を提出してください。
法定外予防接種助成申請書兼請求書(pdf 154 KB)を提出してください。
※医療機関の証明に代えて領収書の提出でも可能です。領収書には患者氏名や予防接種の種類、代金などの記載が必須です。
※助成申請は、予防接種を受けた日から1年以内にお願いします。